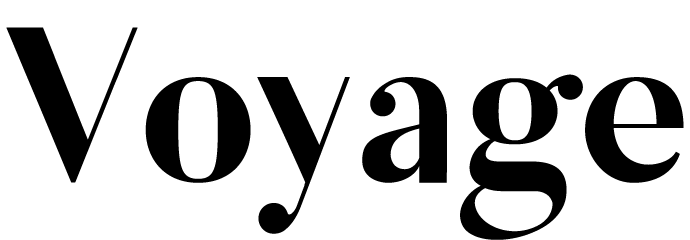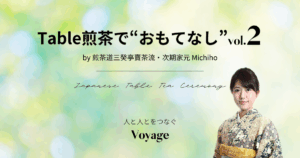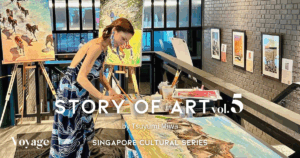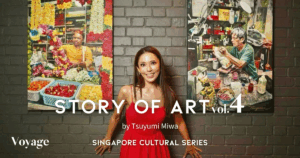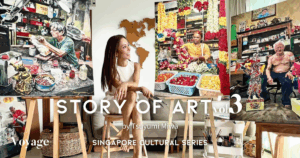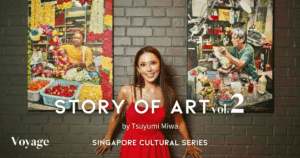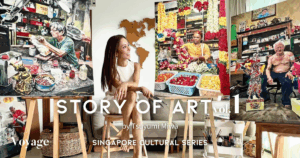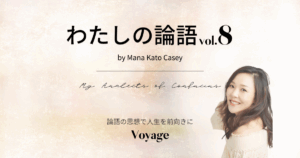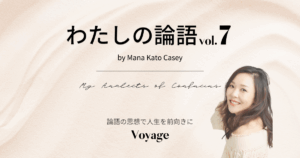「献茶(けんちゃ)」という言葉を、耳にしたことがあるでしょうか。
それは、神前にお茶を捧げ、感謝と祈りの心を表す日本の伝統儀礼のことです。季節を問わず、自然や祖先、日々の恵みに感謝の気持ちを込めて、「香(こう)」「菓子(かし)」「煎茶(せんちゃ)」の順にお供えします。
静かな所作の中に、心を整え、感謝をかたちにする―それが献茶です。煎茶を淹れる手法には「献茶式」と呼ばれる特別な点前(てまえ)があり、これは家元または後継者のみに代々伝えられてきたもの。
湯を注ぎ、香りを立たせ、一煎を神前に捧げる一連の動きは、茶を通して“祈り”を表す、最も静かな儀式ともいえます。
さて、”若宗匠(わかそうしょう:茶道における次期家元の有力候補に与えられる呼称)”として初めての献茶ということもあり、このたびの”献茶祭(2025年10月13日に開催)”は、私自身にとって2025年の中でも特に大切な行事でした。

「広島護国神社」という厳かな場において、神前に一煎の煎茶を捧げるという体験は、煎茶道を伝承する者としての初心を改めて見つめ直す時間でした。
煎茶を捧げるという行為は、単に技術を披露するものではなく、心を静め、祈りを形にする行為です。だからこそこの体験を、記録としてだけでなく、より多くの方に知っていただきたいと感じました。
― 献茶の歴史的背景 ―
日々の茶会を意識したお稽古や、お茶会の実体験とは異なり、献茶では「香」「菓子」「煎茶」をお供えします。
これは古来、仏教や神道において“香・花・灯・茶”などを供える儀礼に由来しています。
煎茶道における献茶は、自然や人、祖先への感謝を「一煎の茶」に託して捧げる儀式で、静かな所作の中に、天地の調和と人への敬意が込められています。
― 献茶の心・精神 ―
献茶における中心の精神は、「感謝」と「調和」。
それはお客様を迎える茶会の心と通じていますが、同時に、より深いところで“祈り”へと行きつきます。
煎茶を通して自らを整え、皆の幸せや健康を願います。その心こそが、献茶の本質であり、私たちの流派である「三癸亭賣茶流」が長く大切にしてきた教え「調和の美」にも通じています。
― 学びと実践を通して ―
明治時代に瀬戸内海を中心に支部が広がった「三癸亭賣茶流」。私も献茶式を家元から直接学び、一人での稽古を重ねるうちに、
自然と先代への感謝が湧き上がってきました。
「三癸亭賣茶流」の点前は、シンプルでありながら最小限の美しい動きの中に、深い精神性が息づいています。
一煎ごとに手を合わせるような気持ちで茶を淹れる時間は、まるで祈りのようであり、自分が伝統の一端を担っていることを静かに実感する瞬間でした。
― 現代へのつながり ―
現代では「祈る」や「捧げる」といった行為が、日常の中から少しずつ姿を消しつつあります。けれども、テーブルで茶を淹れる時間の中にも、その心を取り戻すことはできるのではないかと思うのです。
空間を整え、湯を沸かし、煎茶を丁寧に注ぐ。それだけで心は澄み、穏やかな祈りの場が生まれます。
テーブル煎茶を通して、私は“献茶のこころ”を日常へと橋渡ししていきたいと考えています。
今回の献茶を通じて、「今」という瞬間を丁寧に生きること、そしてこの文化を次の世代へと継承していくことの大切さを
あらためて感じました。
煎茶を捧げるという行為は、人と自然、過去と未来をつなぐ小さな祈りです。
これからもその一煎を通して、”心が通い合う時間”、”人と人とが繋がる時間”を紡いでいきたいと思っています。