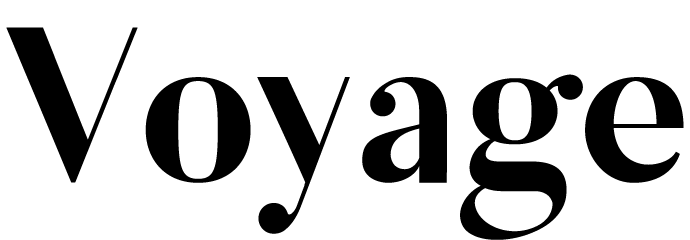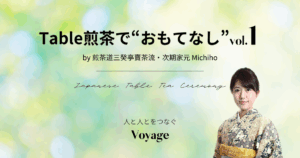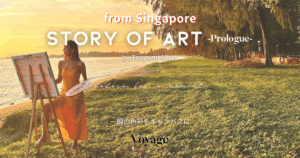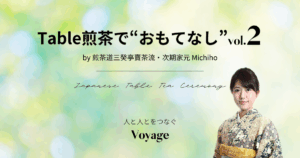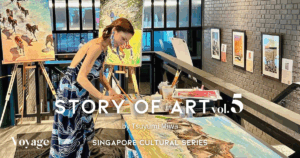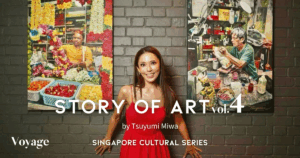はじめまして。伊賀 満穂(いが みちほ)と申します。
私は、煎茶道三癸亭賣茶流(せんちゃどう さんきてい ばいさりゅう)の家元を父に持ち、幼いころから煎茶道が身近にある環境で育ちました。


自然とお茶のある暮らしに親しみながら成長し、その後、都内での会社員生活を経て、自らのサロンを立ち上げ、テーブルとイスで気軽に煎茶を楽しむ「Table煎茶」のレッスンを主宰するようになりました。


また、約1年半前までの3年間は中国・北京に在住し、現地では中国茶の魅力にも深く触れる機会を得ました。中国茶藝師の国家資格を取得し、現在は愛媛県を拠点に、日本茶だけでなく中国茶の文化や美しさも、多くの方にお伝えしています。
お茶は、国や形式を超えて、人と人との心をやさしくつなぐ力があると感じています。そんな思いを込めて、この連載を通じて少しずつ私の「Table煎茶」の世界をご紹介できれば幸いです。

そもそも“煎茶道”とは?
多くの方がまず思い浮かべるのは、お抹茶を点てる“茶道”かもしれません。日本の茶道と言われるものには“抹茶道、茶の湯”と言われるものと“煎茶道”があります。その由来は、18世紀ごろ、江戸時代中後期の日本にさかのぼります。
当時の知識人や芸術家たち、いわゆる“文人”たちが交流の場で煎茶を淹れて楽しんだことから広まり、やがて煎茶道として受け継がれるようになりました。

床の間に屏風を飾り、季節の草花を庭から摘んで生け、お茶を丁寧に淹れてともに味わいます。煎茶道はそうした風雅な営みの中で発展し、厳格な作法に縛られることなく、自由に“風流”を楽しむことが特徴です。
“Table煎茶”というかたち
私のサロンでは、この煎茶道を現代の暮らしの中でも取り入れやすいかたちでご紹介しています。伝統を大切にしながら、もっと自由に、そして自分らしく楽しむ「Table煎茶」というスタイルです。
大切にしているのは、お茶・お菓子・お花・うつわの4つの要素を調和させ、美しい空間を創ること。
お客様が季節の移ろいを感じ、その場に集った方々との会話が自然と生まれるような、心地よいひとときを演出すること。
その時間をご一緒できることが、私にとって何よりの喜びです。


煎茶道で用いられる道具は、急須や小ぶりの煎茶碗などが中心で、中国茶の茶器とよく似ています。
一つひとつの道具に心を込めて向き合い、お茶を淹れる時間そのものが、味わいを深め、心を穏やかに整えてくれます。
お茶のある空間を通して、人と人の心がやわらかくつながっていく——
そんな時間を、これからも大切にしていきたいと思っています。
今後はこの連載を通して、「季節とともに楽しむTable煎茶のある暮らし」の魅力について、少しずつご紹介していけたらと思っています。どうぞ、これからよろしくお願いいたします。