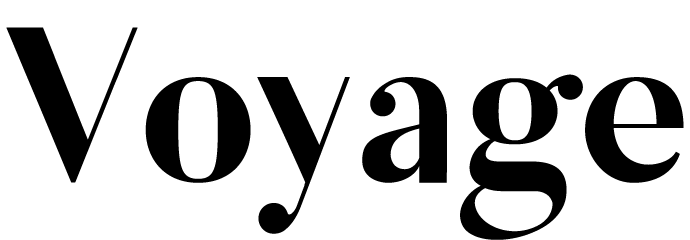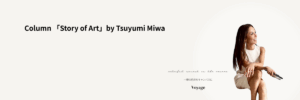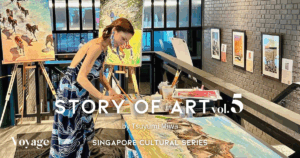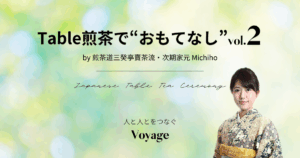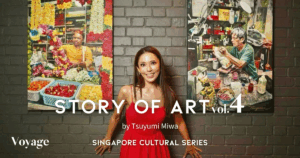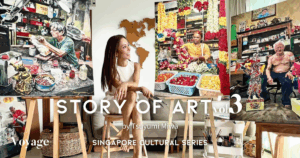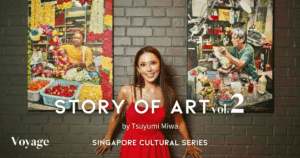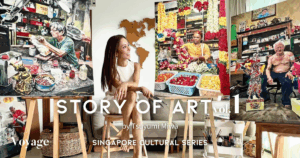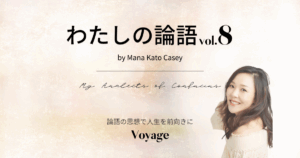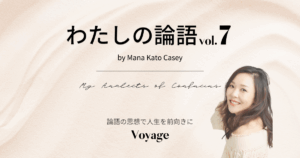書と絵画に親しんだ幼少期、女優としてスクリーンに立ち、アナウンサーとして言葉を届けた日々——
Tsuyumi Miwa(三輪つゆ美)さんの人生には、つねに芸術が寄り添ってきました。
日本、イタリア、オーストラリア、そして現在、拠点とするシンガポール。多様な文化に触れてきた彼女が今、アーティストとして再び絵筆をとり、色彩と光の対話を通して描くのは、個人の記憶と”シンガポール”という多文化・他民族が共生する土地の記憶が交差する情景。
「Voyage」での本連載「Story of Art」では、まず、三輪つゆ美さんが近年発表した「Singapore Cultural Series」において、シンガポールの多文化社会を支える無数の”日常のヒーロー”たちにフォーカス!
彼女が歩んできた芸術の軌跡と、作品に込められた想いを、ひとつずつ紐解いていきましょう。
【Story of Art Vol.6】伝統中国人形劇師──指先が紡ぐ、動きの中に息づく物語

かつてシンガポールの寺院では、色鮮やかな幕の奥から人形たちが語り出す声が響いていました。
17世紀に福建省で生まれた
「ka-lé-hì 傀儡戲(嘉禮戲)」は、いまも職人たちの手によって命を吹き込まれ、文化の記憶を語り続けています。
“A puppet is more than wood and cloth—it is a storyteller, a vessel of culture, and a bridge between past and present, bringing legends to life with every movement”
ーー”人形は、木と布でできた単なる道具ではない。それは物語を語る者であり、文化を運ぶ器であり、
過去と現在をつなぎ、ひとつの動きごとに伝説を甦らせる存在である”
福建で生まれた、時を超える芸術 ー 幕の向こうの“語り手たち”
福建省で17世紀に誕生した「ka-lé-hì 傀儡戲(嘉禮戲)」は、物語と音楽、即興性を融合させた伝統芸能。 シンガポール、台湾、マレーシアの福建語圏でいまも息づき、人々に愛され続けています。
寺院の小さな舞台で、操り手たちは幕の後ろに隠れ、布製の人形を巧みに操ります。 神話や歴史、伝説を題材にした物語には、神々や英雄、精霊が登場し、そこには笑いや教訓が織り込まれています。
京劇などの舞台とは異なり、布袋戯では語り手自身の声が登場人物を生かすのが特徴。人形の小さな仕草や視線の動きひとつで、善と悪がせめぎ合う世界が生まれ、観客はその物語に引き込まれていきます。
シンガポールで息づく情熱”ドリーンと劇団「格藝(Ge Yi)」の存在”
現代の娯楽が主流となったいまでも、シンガポールにはこの伝統芸能を守り続ける人形師たちがいます。彼らは手首のひと振りごとに物語を蘇らせ、未来へと文化の灯をつないでいます。
そのひとりが、*Ge Yi(格藝)*という劇団を率いるドリーン。彼女と劇団の姿を描いた一枚の絵は、「ka-lé-hì 傀儡戲(嘉禮戲)」の緻密で躍動的な美しさを伝えています。彼女たちの舞台は、布袋戯の命を次世代へと伝える存在。彼女たちの姿を描いた絵画には、繊細で力強い動きと、伝統芸能への深い敬意が込められています。
文化そのものを再生し、過去の記憶を現代に息づかせる“生きた物語”と言えるのです。
布袋戯は、静かな動きの中に宿る物語の芸術。 そのひとつひとつの手の動きが時間を超えて私たちを結びつけ、古代からの知恵と美意識をいまに伝えています。
三輪つゆ美さんが「Singapore Cultural Series」で描き出すのは、そうした“生きた文化の記憶”です。
次回は、また別の”日常のヒーロー”が登場!
その一筆一筆の向こうに広がるシンガポールの多様な文化の物語を、どうぞお楽しみに。
こちらの連載は、”毎月の満月の日”に更新されます。
次回の連載は、2025年12月5日(金)を予定しています。